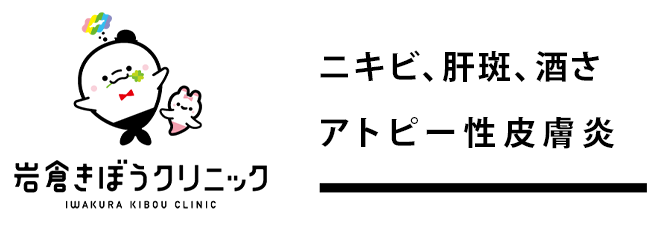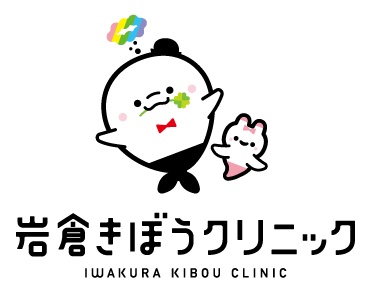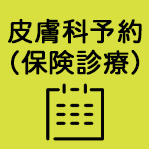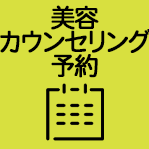「足の爪が白く濁る」「爪が厚くなる」。その変化を、年のせいだと諦めていませんか?その症状、放置すれば家族にうつる「爪白癬」かもしれません。しかし、安易な自己判断は禁物です。
実は、爪の異変は糖尿病といった重い病気のサインである可能性も。そして、最も知っておくべきは「爪水虫に効く市販薬は存在しない」という事実です。この記事では、皮膚科専門医が爪のトラブルの正しい見分け方から治療法までを徹底解説します。手遅れになる前に、爪からのサインを正しく受け止めましょう。
足の爪が白いのは水虫?爪白癬の症状と3つの見分け方
「最近、足の爪が白く濁ってきた」「爪が分厚くなって、靴を履くと痛い」。 このようなお悩みをお持ちではありませんか。
ご高齢の方の足の爪が白くなる原因で最も多いのは、「爪白癬(つめはくせん)」です。 これは一般的に「爪水虫」と呼ばれ、白癬菌というカビの一種が爪に感染して起こります。
見た目が気になるだけでなく、放置すると爪が変形して歩きにくくなることもあります。 また、ご自身だけの問題ではなく、ご家族にうつしてしまう可能性も考えられます。
しかし、足の爪が白くなる原因は爪水虫だけではありません。 自己判断で市販薬を使い続けると、症状が悪化することもあります。 ここでは、爪白癬の症状や他の原因との見分け方について、皮膚科専門医が詳しく解説します。
爪白癬(爪水虫)の初期症状と進行後の見た目の変化
爪白癬は、痛みやかゆみといった自覚症状がほとんどありません。 そのため、ご自身では気づかないうちに進行してしまうことが多い病気です。 ご自身の爪の状態と見比べて、早期発見に繋げましょう。
【初期症状】
- 爪の先端や側面に、白い筋や点状の濁りが現れる
爪の先の方から、縦にスジが入るように白くなるのが典型的な始まり方です。 - 爪の表面のツヤがなくなり、カサカサしてくる
健康な爪にある自然な光沢が失われ、少し粉をふいたように見えることがあります。 - 爪が以前より少し厚みを増してくる
この段階では変化がわずかなため、「年のせいかな」と見過ごされがちです。
【進行後の症状】 初期症状を放置すると、白癬菌は爪の奥深くまで侵食します。 そして、以下のような変化が爪全体に広がっていきます。
| 症状の変化 | 具体的な見た目 |
|---|---|
| 色の変化 | 白い濁りが、黄色や褐色、黒っぽい色へと濃くなります。 |
| 厚みの変化 | 爪がどんどん厚くなり(肥厚)、靴に当たって痛むことがあります。 |
| 形の変化 | 爪がもろくなり、ポロポロと崩れたり、変形したりします。 |
| その他の変化 | 崩れた爪の間に細菌が入り込み、嫌な臭いを発することがあります。 |
進行すると、爪が分厚くなりすぎて爪切りで切れなくなることも珍しくありません。 また、変形して巻き爪の原因になったり、歩行時に痛みを感じたりすることもあります。 足の裏や指の間に水虫がある方は、爪にも感染している可能性が高いため特に注意が必要です。
爪の乾燥や加齢、靴による圧迫が原因の場合との違い
爪が白っぽく見える原因は、爪白癬だけではありません。 加齢や生活習慣が原因で、爪が変化することもあります。 自己判断は禁物ですが、爪白癬との違いを知っておくことは大切です。
1. 乾燥や加齢による変化 年齢を重ねると、皮膚と同じように爪も水分を失い、乾燥しやすくなります。
- 爪甲縦条(そうこうじゅうじょう)
爪に縦の筋が入る状態です。筋の部分は白っぽく見えることがあります。
これは病気ではなく、多くは加齢による自然な変化の一つです。 - 脆く割れやすい
乾燥によって爪がもろくなり、二枚爪になったり、先端が白く欠けたりします。
2. 靴による圧迫や外傷 サイズの合わない靴や、指先に負担のかかる靴を履き続けることも原因となります。
- 爪の肥厚・変形
慢性的な圧迫により、爪が厚くなったり、黄色っぽく変色したりすることがあります。
【爪白癬との見分け方のポイント】
| 爪白癬 | 乾燥・加齢・圧迫 | |
|---|---|---|
| 濁りの特徴 | 筋状・斑点状に濁り、徐々に広がる | 均一に白っぽい、または縦筋に沿って白く見える |
| 進行 | 治療しないと悪化し、他の指にうつることもある | 進行は緩やかで、他の指にうつることはない |
| 質感 | もろく、ポロポロと崩れる | 硬く厚くなる、または薄く割れやすくなる |
これらの特徴はあくまで目安です。 正確な診断には、爪の一部を採取して顕微鏡で菌の有無を確認する検査が必要です。
爪カンジダ症など、爪白癬と似ている他の病気
爪白癬の原因である白癬菌以外にも、爪の変化を引き起こす微生物がいます。 その代表的なものが「カンジダ菌」です。
爪カンジダ症 カンジダ菌は、もともと人の体に存在する常在菌の一種です。 しかし、免疫力が低下したときなどに増殖して症状を引き起こします。
- 特徴
爪白癬が爪の先端から始まることが多いのに対し、爪カンジダ症は爪の根元(甘皮の部分)から炎症が起こることが多いのが特徴です。爪の周りの皮膚が赤く腫れて、痛みを伴うこともあります。 - 爪の変化
爪の表面がデコボコしたり、白や黄色、緑色などに変色したりします。 - かかりやすい人
水仕事が多い方や、指しゃぶりの癖があるお子さん、糖尿病など免疫力が低下する持病をお持ちの方に多く見られます。
その他の病気 まれですが、以下のような皮膚の病気が爪に症状として現れることもあります。
- 爪乾癬(つめかんせん)
皮膚の病気である乾癬の症状が、爪に現れるものです。爪に点状のへこみができたり、厚くなったり、剥がれたりします。 - 爪甲剥離症(そうこうはくりしょう)
爪の先端が下の皮膚から剥がれて浮き上がり、その部分が白く見えます。外傷や薬剤、甲状腺の病気など、様々な原因で起こります。
これらの病気は、爪白癬とは治療法が全く異なります。 正しい治療のためには、菌の種類や原因を特定する検査が欠かせません。
糖尿病や血行障害が原因で爪が白くなるケース
糖尿病や足の血行障害といった持病をお持ちの方は、爪のトラブルが起こりやすくなります。 爪の変化は、全身の健康状態を反映する重要なサインでもあるのです。
糖尿病と爪白癬 糖尿病をお持ちの方は、健康な人に比べて爪白癬にかかりやすいことが知られています。 これは単に「かかりやすい」だけでなく、放置すると深刻な事態を招く危険な合併症です。
感染しやすい理由
- 免疫力の低下
血糖コントロールが不良な状態が続くと、体の抵抗力が落ち、白癬菌などの感染症にかかりやすくなります。 - 血行障害
糖尿病の合併症である末梢血管障害により、足先への血流が悪化します。爪に十分な栄養や酸素が届かず、健康な爪を維持しにくくなります。 - 神経障害
足先の感覚が鈍くなるため、小さな傷や靴ずれに気づきにくくなります。その傷が菌の侵入口となってしまうのです。
- 免疫力の低下
重症化のリスク
糖尿病の方が爪白癬を放置すると、爪の変形によってできた傷から細菌が入り込みます。
そこから、足が赤く腫れ上がる「蜂窩織炎(ほうかしきえん)」や、治りにくい「足潰瘍」を引き起こす危険性があります。
最悪の場合、足を切断することにもなりかねないため、迅速な診断と早期介入が非常に重要です。
血行障害による爪の変化 閉塞性動脈硬化症など、足の血管が細くなる病気でも爪は白っぽく変化します。 これは、爪を作るために必要な血液が不足するために起こる現象です。
爪の異変は、「たかが爪の問題」と軽視できるものではありません。 特に糖尿病などのご病気をお持ちの方は、爪の変化に気づいたらお早めに皮膚科にご相談ください。 当院では、患者様一人ひとりの背景にあるご病気も考慮しながら、最適な治療法をご提案いたします。 岩倉市だけでなく、北名古屋市、小牧市、一宮市、江南市からもアクセス良好ですので、お気軽にご来院ください。
皮膚科で行う爪白癬の治療法!費用と期間の目安
「足の爪が白く濁ってきた」「分厚くなって靴が痛い」。 もしかして爪水虫(爪白癬)かもしれないと、ご心配ではありませんか。
爪白癬は自然に治ることはなく、放置すると見た目が悪化するだけではありません。 ご家族など、大切な方にうつしてしまう可能性もある病気です。
しかし、ご安心ください。皮膚科では、症状や患者様一人ひとりの健康状態に合わせた治療が可能です。 治療には根気が必要ですが、きちんと続ければ、きれいな爪を取り戻せます。 ここでは、皮膚科で行う主な治療法について、費用や期間の目安とともに詳しく解説します。
保険適用で始める塗り薬(外用薬)治療の効果と限界
爪白癬の治療で、まず基本となるのが保険適用の塗り薬(外用薬)です。 爪の表面に直接薬を塗ることで、原因である白癬菌の増殖を抑えます。 特に、以下のような方に適した治療法です。
- 症状が爪の先端や表面の一部にとどまっている初期段階の方
- 肝臓の持病や、他の薬との飲み合わせで飲み薬が使えない方
塗り薬は、飲み薬と比べて全身への影響が少ないのが大きな利点です。
塗り薬(外用薬)治療のポイント
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 治療期間の目安 | 足の爪が根元から先端まで完全に生え変わるには、約1年〜1年半かかります。そのため、症状が改善しても自己判断で中断せず、根気強く毎日塗り続けることが重要です。 |
| 費用の目安(3割負担) | 1本あたり約1,500円〜2,500円程度です(薬の種類により異なります)。 |
| 効果的な使い方 | ・入浴後など、爪が清潔で水分を含んで柔らかくなっている時に塗る ・爪の表面だけでなく、爪と皮膚の境目や爪の裏側にもしっかりと行き渡らせるように塗る ・医師の指示通り、毎日欠かさず継続して使用する |
ただし、塗り薬には限界もあります。 爪は硬いケラチンというタンパク質でできているため、分厚くなった爪の奥深くまで薬の成分を浸透させることは容易ではありません。 そのため、進行してしまった爪白癬を塗り薬だけで治すのは難しい場合があります。 治療効果を見ながら、飲み薬への切り替えや併用を検討することもあります。
飲み薬(内服薬)の副作用と肝臓への影響について
爪の変形が進んでいる場合や、複数の爪に症状が広がっている場合には、飲み薬(内服薬)による治療が中心となります。 体の内側から血流に乗って薬剤が爪の組織に直接届くため、塗り薬よりも高い治療効果が期待できます。
しかし、効果が高い分、副作用の可能性も正しく理解しておく必要があります。 特に注意が必要なのが、まれに起こる肝臓への影響です。 そのため、飲み薬による治療では、安全性を確認するために定期的な血液検査が必須となります。
飲み薬(内服薬)治療で知っておきたいこと
- 定期的な血液検査
治療開始前と治療開始から1〜2ヶ月後に血液検査を行います。
肝機能などに異常がないかを医師が確認しながら、安全に治療を進めます。 - 副作用
まれに胃腸の不快感や、発疹などが出ることがあります。
気になる症状があれば、自己判断で中止せず、すぐに医師にご相談ください。 - 他の薬との飲み合わせ
一部の薬とは一緒に服用できない場合があります。
現在服用中のお薬がある方は、必ずお薬手帳をご持参ください。
特に、前の章で解説したように糖尿病の持病をお持ちの方は注意が必要です。 糖尿病患者様の爪白癬は、足潰瘍や二次的な細菌感染といった深刻な合併症を引き起こす危険性をはらんでいます。 このような重症化リスクが高い方には、迅速な診断と早期の治療介入が非常に重要です。
医学的には、テルビナフィンやイトラコナゾールといった内服薬が、中等度から重度の爪白癬に対する第一選択薬と考えられています。 患者様一人ひとりの健康状態を十分に考慮し、最適な治療計画を立ててまいります。
市販薬は効く?皮膚科の薬との違いと正しい選び方
ドラッグストアなどで「水虫薬」として販売されている市販薬を試そうか、と考える方もいらっしゃるかもしれません。 しかし、ここで非常に重要なことをお伝えします。 現在のところ、爪白癬(爪水虫)に効果があると国から承認された市販薬はありません。
市販されている水虫薬は、あくまで皮膚の水虫(足白癬)を対象としています。 爪は皮膚とは構造が異なり、硬く厚いため、市販薬の成分では爪の内部に潜む白癬菌まで到達できないのです。
自己判断で市販薬を使い続けることには、以下のようなリスクが伴います。
- 効果がない
爪の奥の菌まで薬が届かず、時間とお金を無駄にしてしまう可能性があります。 - 症状の悪化
適切な治療が遅れる間に、白癬菌は爪の奥へと侵食し、症状が悪化してしまいます。 - 診断の誤り
爪が白くなる原因は爪白癬だけとは限りません。
他の病気の可能性を見逃し、治療の機会を失ってしまう危険性もあります。
爪の変色や変形が気になったら、市販薬を試す前に、まずは皮膚科を受診してください。 皮膚科では、爪の一部を採取して顕微鏡で菌の有無を直接確認する検査を行います。 原因を正確に診断することが、完治への一番の近道です。
当院では、患者様一人ひとりの爪の状態を丁寧に診察し、生活背景や持病なども考慮した上で最適な治療法をご提案いたします。 岩倉市はもちろん、北名古屋市、小牧市、一宮市、江南市からもアクセスしやすい場所にありますので、爪のことでお悩みでしたら、お気軽にご相談ください。
家族にうつさない!爪白癬の感染予防と再発を防ぐ5つの習慣
ご自身が爪白癬(爪水虫)と診断され、「大切な家族にうつしてしまったらどうしよう」とご心配ではありませんか。
爪白癬の治療は根気が必要ですが、それと同じくらい大切なのがご家庭での感染対策です。 原因である白癬菌は、目に見えないところで感染を拡げる力を持っています。 しかし、菌の性質を正しく理解し、ポイントを押さえた対策をすれば、感染のリスクは大幅に減らせます。
ここでは、ご家族を守り、ご自身のつらい症状を繰り返さないための具体的な5つの習慣を、皮膚科専門医が詳しく解説します。
主な感染経路と家庭内で注意すべきこと(バスマット・スリッパ)
爪白癬の感染は、菌そのものが直接うつるわけではありません。 感染した方の爪や皮膚から剥がれ落ちた「角質(あか)」に白癬菌は潜んでいます。 この角質が付着した場所を、ご家族が素足で歩くことで感染が成立するのです。
特に、家庭内では湿気と角質が溜まりやすい場所が、菌の温床となります。
【家庭内で特に注意したい場所と対策】
バスマット・足拭きマット
お風呂上がりは皮膚がふやけて角質が剥がれやすく、水分も多いため、菌にとって最も増殖しやすい環境です。- 対策
ご家族との共有は避け、個人用のタオルやマットを用意しましょう。
使用後は毎回、風通しの良い場所に干して完全に乾かすことが重要です。
- 対策
スリッパ・サンダル
素足で履く機会が多いスリッパも、汗や角質が溜まりやすく注意が必要です。- 対策
ご自身専用のスリッパを決め、他のご家族が履かないようにしましょう。
素材は、通気性の良いものや、洗いやすいものを選ぶのがおすすめです。
- 対策
床(フローリング、畳)
目には見えませんが、リビングなどの床にも菌を含んだ角質は落ちています。- 対策
こまめに掃除機をかけ、菌が潜む角質を取り除くことを心がけましょう。
白癬菌は乾燥に強く、数ヶ月間は感染力を保つことがあるため、定期的な掃除が不可欠です。
- 対策
洗濯物は分けるべき?爪白癬菌を拡げない洗濯・掃除方法
「菌がついた靴下を、家族の衣類と一緒に洗っても大丈夫?」 これは、患者様からよくいただくご質問の一つです。
結論から言うと、通常の洗濯で他の衣類に菌がうつる可能性は低いと考えられます。 洗濯機の十分な水量と水流、そして洗剤の洗浄力によって、ほとんどの白癬菌は洗い流されるからです。 そのため、過度に神経質になって洗濯物を分ける必要はありません。
ただし、より安心して感染対策を行いたい場合は、以下の点を心がけると効果的です。
【洗濯で心がけたいポイント】
- 洗濯後はすぐに干す
洗濯槽の中に湿った衣類を長時間放置すると、菌が増殖する原因になります。
洗濯が終わったら、できるだけ早く取り出して干しましょう。 - 完全に乾燥させる
白癬菌は湿気を好みます。天日干しで紫外線を当てるか、乾燥機を利用して、衣類を完全に乾かすことが菌の増殖を抑える上で非常に重要です。
【掃除で心がけたいポイント】
- こまめな掃除と換気
前述の通り、床に落ちた角質を除去するために、こまめに掃除機をかけましょう。
同時に、部屋の換気を行い、湿度を下げて乾燥した環境を保つことが、菌が活動しにくい環境づくりに繋がります。
このような「環境衛生」への配慮は、再発予防の観点からも極めて大切です。
再発させないための正しい足の洗い方、爪の切り方、靴の選び方
爪白癬は、一度治っても生活習慣が元に戻ると再発しやすい病気です。 再発を防ぐためには、日々の「足の衛生管理」が何よりも重要になります。 特に、
まとめ
今回は、足の爪が白くなる原因「爪白癬」について、症状の見分け方から治療法、ご家庭での予防策まで詳しく解説しました。
爪の濁りや厚みは、見た目が気になるだけでなく、放置すれば歩行に影響が出たり、大切なご家族にうつしてしまったりする可能性があります。 自己判断で市販薬を使っても爪の奥に潜む菌には届かず、かえって治療が遅れてしまうことも少なくありません。
爪白癬は、皮膚科で原因をきちんと特定し、根気強く治療を続ければ治せる病気です。 「爪の様子がいつもと違うな」と感じたら、それは体からの大切なサインかもしれません。一人で悩まず、まずは気軽に皮膚科の専門医へ相談してみましょう。
参考文献
- Gupta AK, Liddy A, Magal L, Shemer A, Cooper EA, Saunte DML, Wang T. Onychomycosis in Diabetics: A Common Infection with Potentially Serious Complications. Life (Basel, Switzerland) 15, no. 8 (2025).
追加情報
[title]: Onychomycosis in Diabetics: A Common Infection with Potentially Serious Complications.
糖尿病患者における爪白癬:一般的な感染症と潜在的に深刻な合併症 【要約】
- 爪白癬は糖尿病患者においてよく見られる臨床的に重要な合併症である。
- 二次的な真菌および細菌感染症、足部潰瘍、そして進行した場合には切断のリスクを高める。
- 糖尿病患者における爪白癬の有病率が高い要因には、年齢、末梢血管疾患、血糖コントロール不良、神経障害、不適切な足の衛生状態、爪の травма がある。
- 皮膚糸状菌が最も一般的な病原体であるが、糖尿病患者は様々な抗真菌薬感受性を示すカンジダ属を含む混合感染を起こしやすい。
- 迅速な診断と早期介入は合併症を予防するために重要である。
- テルビナフィンやイトラコナゾールなどの全身性抗真菌薬は、特に中等度から重度の爪白癬に対して第一選択薬と考えられている。
- 薬物相互作用、腎臓、肝臓、代謝の併存疾患は、個別の治療計画を必要とする場合がある。
- 軽度から中等度の疾患の患者、または経口療法に禁忌がある患者には、エフィナコナゾールやタバボロールなどの局所薬が実行可能な代替手段を提供する。
- 足の衛生に関する教育、水虫の迅速な治療、環境衛生などの補助的対策は、再発と再感染を防ぐ上で重要である。
- 本レビューでは、糖尿病患者における爪白癬の疫学、診断、および治療上の考慮事項をまとめ、この高リスク集団におけるアウトカムを改善するために個別化されたケアの必要性を強調する。
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40868932[quote_source]: Gupta AK, Liddy A, Magal L, Shemer A, Cooper EA, Saunte DML and Wang T. “Onychomycosis in Diabetics: A Common Infection with Potentially Serious Complications.” Life (Basel, Switzerland) 15, no. 8 (2025): .
—————ご来院頂いている主なエリア————————
愛知県・北名古屋市、小牧市、一宮市、江南市、名古屋市、清須市、
豊山町、岩倉市、春日井市、稲沢市、犬山市、大口町、扶桑町
岐阜県・岐阜市、各務ヶ原市、可児市、美濃加茂市